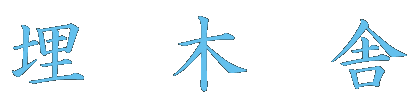セミョーノフ中佐がスワロフの艦橋にあがって海域を一望したときは、東郷の艦隊は試射の段階を終わったばかりだった。
バルチック艦隊は、東郷の試射の段階においてすでに前述のような惨況を呈した。本格的な射撃が始まればどうなるのであろう。
セミョーノフが艦橋にのぼったとき、旗艦スワロフにつづく戦艦アレクサンドル三世と同ボロジノという、ロシア帝国の威信の象徴ともいうべき二隻の戦艦が、火災をおこして淡黄色の煙につつまれていた。
(なんということだ)
と、セミョーノフは思ったが、しかし彼の感想を吹っ飛ばすよにして例の薪
が飛んで来た。どの薪も肉眼で見えたし、どの薪もみな彼の立っている艦橋をめがけて襲ってくるように思われた。艦橋などに立っていられるものではなかった。彼はあわただしく艦橋を降りた。
しかしどこへゆくあてもない。
(艦尾へ行こう)
と、ノートを持ったまま駈けだした。途中、足の踏み場もないほどに落下物や死体などがころがっていた。信号所も距離測定所も着弾観測所もみな日本の砲弾のために破壊されており、旗艦スワロフは軍艦として備えている目と耳の機能をすでに失いつつあることをセミョーノフは知った。
一方、三笠の艦橋では秋山真之もノートをとっていた。この日本海軍における文章家はセミョーノフのように英雄礼讃
の物語を書くことを義務づけられているわけではなく、あとで戦闘詳報を書かねばならないために時々刻々に変化してゆく戦況をメモしているのである。
戦艦オスラービアに火災がおこったのは、三笠が射撃を開始してからわずか五分後の二時十五分である。
ついに東郷艦隊は彼我五千メートル以内に踏み込んだ。この肉薄の状況は、真之がかつて造語した
「舷々 相
摩 す」 という形容にやや近づきつつあった。五千メートル以内に入ると、東郷艦隊から発射される砲弾の命中率が飛躍的によくなった。
真之は相変らず双眼鏡を用いなかった。肉眼で見ても、すでに敵艦隊の状況はよく見えた。
戦艦オスラービアの損害は大きく、大檣は折れ、煙突は吹っ飛び、火災は艦内の各所におこっていた。しかもこの艦は水線部を砲弾で縦横につらぬかれており、その弾孔からの大量の海水が入りつつあった。
「オスラービア、傾く」
と、真之はメモした。
旗艦スワロフのマストも折れており、艦体は火炎でつつまれていた。真之の肉眼では見えなかったが、加藤友三郎の双眼鏡にはスワロフの甲板上を駈けまわっている消化隊の様子が手にとるように見えた。
火災のもっともひどいのは戦艦アレクサンドル三世であった。
これら火を背負って駈けまわる各艦の猛煙が海上に薄絹のように垂れた濛気と入りまじって、思わぬ煙幕をなした。このため日本側は照準が困難となり、ほんのしばらくながら射撃を中止するという処置までとられた。 |