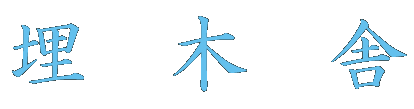「なんと、皇后宮亮
どのには、遅いお着きよのう。いまごろ、この敦賀つるが
へは入られたか」
彼を見ると、小松中将こまつちゅうじょう
維盛これもり は、すぐ言った。
皮肉にひびいたか、経正は、ちょっと、色をなした。
軍議への席へ着いたとたんである。満座の眼は自分へ向かってそそがれた抗弁ではないまでも、何か一言、証を立てないわけにはゆかなくなった。
「心外なことを承うけたまわ
るものです。遅れは、経正の怠りではありません。先の軍が行きつかえていたため、海津かいづ
でも愛発あらち の関でも、むなしい日を余儀なくされ、ようやく今夕、敦賀へ入った有様です。そして、物具もののぐ
を解くいとまもなく、お迎えにまかせてこれへ参ったのに」
「したが、陣中のうわさでは、皇后宮亮どのには、このたびの出勢を、遊山ゆざん
と間違われているのではないか・・・・などと沙汰する者があるが」
「ははあ、さては海津の滞陣の一日、経正が竹生島ちくぶしま
へ詣もう でたるを、人はさように申するのでございましょう」
「人の口端くちは
とて、浅う聞くまい。出陣には、みな妻子に別れを惜しみ、帰る日もありやなしと、都を振り向いて、立ち出でたる者ばかりなのに、一軍の将たるおことが、舟を泛うか
べて、悠々ゆうゆう 、竹生島詣でなどしていたら、陰口もむりではあるまい」
「こは心得ぬ仰せです。北陸の戦いこそは、平家の浮沈、あわれ、勝たし給えと、一門の名を願文がんもん
につらねて、戦捷せんしょう の祈願をこめて戻りまいたことも、大将軍のお耳へは、さように、ゆがめられたうわさとなって、はいっておりましたか」
経正は、しかし、もう口をつぐんだ。あとは、みずから胸をなだめようと努めている姿に見える。
そして、心を静かに、清盛亡き後の一門というものを、客観してみて、
(まあ、これくらいな誤解は、ありがちなことよ)
と、自分の大人気なさにも、自嘲じちょう
されてくるのである。
経正は四十だが、総じて、平家一門の主将は、みな若い。
経盛、教盛のりもり
、頼盛、時忠あたりが、年長者だが、それとて、五十がらみである。
平家の総領で、清盛の世継ぎの右府宗盛にしてさえ、やっと三十七。
維盛にいたっては、まだ、二十四歳の公達に過ぎなかった。小松重盛の嫡男で、嫡家の人たるところから、富士川の合戦にも、こんどの北陸追討にも、総大将となっているが、年齢からいっても、三軍の総帥そうすい
は重荷すぎる。無理な若さといってよい。
経正は、年上として、そう気づいた。
それと、大将軍、副将軍、侍大将など帷幕いばく
は、みな叔父おじ 甥おい
か、従兄弟いとこ 仲なか
か、兄弟か、何しろ、内輪同士すぎるのである。そのため、狎な
れやすさや、わがままが、戦場においてすら、とかく振る舞われがちだった。
ときには、美しいともいえる肉親愛に見えもするが、おりには、しまつの悪い縺もつ
れにもなる。 「お互い、つつしまねばならぬ」 と、その点も経正はひそかに痛感するのだった。 |