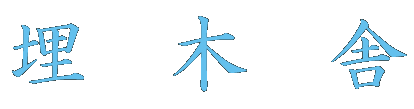その艶
なる公達が。
そして、まだ二十四の君が。
いま、強武者こわむしゃ
十万と号する三軍を率い、驍勇ぎょうゆう
、木曾義仲の追討を命じられ、都をあとに、この越路こしじ
へ来ているのだと思うと、多少の不満は覚えても、
「この君を扶たす
けぬことには」
と、情においては、みな一致した。
また、維盛とて、決して、暗愚な大将というわけではない。むしろ、こんどの北陸入りは、いじらしいほど、内心、雪辱せつじょく
を誓っている。
かの、富士川敗戦の汚名をである。
美濃みの
の墨俣すのまた では、新宮行家を破って大勝した。しかし、あのさいの総帥は、宗盛の弟重衡であり、彼の汚名はまだぬぐわれていない。
それかあらぬか、宗盛は、またこんども斎藤別当を、中軍に付けてよこした。実盛の人物は、富士川でよく分かっている。この老人の経験は、おろそかにしまいと思う。
維盛は素直に、彼をそう容い
れている。その気持が、思わず笑くぼになったものである。
「・・・・では、実盛が献策と申す、その策なるものを、聞こうではないか」
経正への誤解を解いて、維盛は、まったく、ことばの調子までを、明るくした。
「斎藤の別当。これへ進んで、詳しゅう、おはなし申し上げよ」
通盛も、上座から、うながした。
「は・・・・はあ」
実盛は、遠くで、うなずいている。どうも、あいまいな顔つきである。身を前屈みに乗り出し、耳のそばへ、手をかざした。なお何か、受け答えでもしようというのらしい。
人びとは、クスクス笑う。それを、気の毒そうに、淡路守清房が、
「さすが、斎藤の別当も、つもるお年、ここ両一年に、とんと、耳が遠くなり、髪もあのように真っ白になった。──
実盛が献策は、自分も動座して聞いていた。実盛に代わり、それがしが申し上げよう」
と、救いを出した。
清房は、維盛の叔父であり、副将の一人。
たれにも、異議はない。その彼が、実盛に代って述べたのは、諸情報に総合された北陸の敵状であり、それへの味方の方針であった。
|