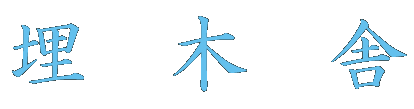義仲は、どこにいようが、夢寐
のまも、上洛の初志を忘れているものではない。
だが、まったく準備成れりとは、いまだいえないものがあった。
── で、麾下きか
の仁科太郎にしなたろう 守弘もりひろ
をして、
「まず、露はらいとして、越前へ先発せよ」
と、さきに派しておいたのだった。
今にも木曾が上洛するかの如く、都の耳を驚かした風声鶴唳ふうせいかくれい
は、この先遣隊がまき起こしたものらしい。
ところが、彼らが越前にはいったころ、かえって都の方から、平家数万の大軍が発向すると聞こえて来たので、狼狽した木曾の先遣隊は、
「燧ひうち
を守れ」
と、急に砦とりで
へ立て籠もって、昼夜、防備にとりかかった。
そこは、四方、取りつく道もないような原始林と山々の峭壁しょうへき
である。
燧山、焼尾山、鍋倉、湯ノ尾、藤倉の支脈などが、向かい合い、重なりあって、自然の嶮けん
をなしている。
深谷の下流しも
の小盆地は、今庄いまじょう とよぶ小部落だった。山あいを、うねり曲がってゆく日野川は、そこでまた、夜叉池川やしゃいけがわ
、板取川を合わせ、遠く、武生たけふ
平野へ流れてゆく。
木曾勢は、川の落ち合いに、堰せき
を作った。
巨木を伐り下ろし、大岩を積みあげ、沢と沢の間に、逆茂木さかもぎ
を引き、杭くい を打ち並べ、あらゆる防禦物を積んで、流れを断った。
「おお、一夜明けるごとに、水かさを上げてくる」
「山々の影も映るほどに」
「見事に、長い湖が出来たぞ。もう船でも浮かめねば、たやすく渡ることはできまい。まして、あまたな兵馬の如きは」
「すばらしい妙計よ。平家の奴輩やつばら
も、胆をつぶすことではあろう」
仁科太郎以下、手を打ち叩いた。もう、備えは万全なりと、ひと息ついた。
この燧ケ城に拠よ
った主なる武将は、仁科守弘のほか、加賀の豪族林六郎光明、匹田二郎俊平、その子、小太郎俊弘、倉光三郎成澄、稲津新介。
それに、加賀富樫郷かがとがしのごう
野々市ののいち の人、富樫とがし
康家やすいえ も加わっていた。
すべて五千人余。
襲よ
せ来る平軍は、数万と聞こえている。十分の一以下の寡兵だった。この天嶮てんけん
と防禦に恃たの んでも、なお砦とりで
に中の人間は、
「死ぬも、生きるもともに」
と、運命を一つにしたことに違いない。
すると、思いがけない味方がふえた。平泉寺の威儀師いぎし
(儀礼の役僧) 斎明さいみょう
が同腹の衆徒一千余人を引き連れて、ここへ加勢に来たのだった。
「天来の御助勢」
と、砦の将士は、いよいよ、これに力をえた。そして、四山のあいだに、不気味な水を満々とみなぎらせ、旗も弓もかくして、ひそまり返っていた。 |