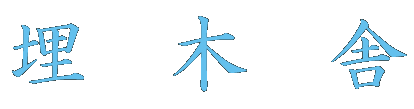平家はやがて、近くの山の上や、中腹や、いたる所に、その先鋒隊
の影を見せはじめた。
維盛たちは、本陣を、岩神山の上においた。
そこへ、よじ登って立った日、維盛は、山麓さんろく
の東西にわたる湖のような水を見て、
「これが、人の業わざ
か」
と、驚き顔をした。
都人の、わけて、桜梅少将おうばいのしょうしょう
といわれた公達育ちの彼には、想像もつかないことであった。
兵馬は、山を埋めるほど、続々着いた。
木ノ芽越えから。── また、分遺隊として、橡ノ木峠を迂回うかい
して来た一軍とも、合流した。しかし、
「どうして、かなたの燧へせまるのか」
となると、これほどな兵力も、ほとんど、無能なものに見えた。手のほどこしようもない。
とこどき、天気のよい日など、燧のいただきの、最も高い岩の上に、鳶とんび
のように、敵兵が見える。
あきらかに、あざ笑っているふうだ。どうかすると、揶揄的やゆてき
な表情を見せ、平軍の方へ向かって、尻しり
などたたく。
「誰た ぞ、遠矢の上手はいないか。あの尻を、射てくれずや」
平家の諸将は、くやしがった。
けれど、しょせん、矢のとどき得る距離ではない。
「われこそ」 などと、強弓を試みる者もいたが、矢は、隔てる水面の瀞とろ
に、鳥の抜ぬ け羽ば
のごとく、みな、浮いてしまうに過ぎない。
「もう幾日ぞ。やがて、五月雨空さみだれぞら
も近づこうに」
対陣は、長くなった。
四月も末になってゆく。
「かかるおりは、また、耳遠殿みみどおどの
に、策を問わせ給うしかございますまい」
滞陣に倦う
み、山気の湿潤しつじゅん に倦み、軍議群議のむなしさにも倦んだ諸将は、ある日、維盛にそう言った。
聞きとがめて、維盛は、
「耳遠殿とは、たれのことかよ」
「斎藤の別当でございまする」
「あ、あの老人か」
笑った。──
そして、考えていたが、
「これへ来てから、実盛は、帷幕いばく
に見えぬが」
「されば、もそっと、燧の根に近い、べtyな山の端はく
に、主馬判官しゅめのほうがん
盛俊もりとし と、わずかな手勢をもって、潜みおりますゆえ」
「なんでまた、老人のくせに、なたそのような小勢で、危ない場所に、伏せ籠こも
っておるのであろう」
「何か。両名の望みだそうで、通盛卿には、御承知だそうですが」
「ではまた、越前殿との、話し合いか」
維盛は、いささか、おもしろくない。
しかし越前三位通盛に訊き
いてみても、よく分からなかった。ただ、両名の希望ゆえ、ゆるしておいたというに過ぎない。
── と、ある日のたそがれ。
その老武者実盛が、長柄を杖に、よぼよぼと、帷幕を訪うて来て、
「こよい、主馬判官盛俊が、ひとりの大法師を連れて参りますが、ごく御内密に、主将の方々も多からぬようにし、篝火かがり
も消して、ひそと、お会い給わりませ」
と告げた。 |