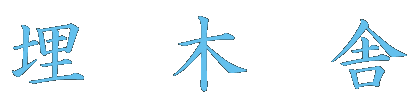まもなく、彼はお座船を訪い、屋形の内で、建礼門院と会っていた。
「・・・・御様体は」
と、まず問うと、女院は、
「いくらか、お熱も降
がりぎみに拝されまする。このぶんならばと、胸をなでおろしておりますが」
みかどの看護みとり
ばかりでなく、やっと自身を支えているような彼女であった。
「やれやれ、それはまず」
宗徳は、ぼんやり言って、
「先ごろから、高松の町屋には、三日疱瘡ぼうそう
とかが流行っていたそうな。みかども、そんなお病ではないかの」
「万乗ばんじょう
の君とはいわれながら、ここでは、ただ一人の医師くすし
さえおりませぬ。このような漂泊さすらい
を、いつまで、強いるのでございましょう」
「何を仰せある」
宗盛は、ちょっと目に角かど
を立てて見せた。
彼女は、国母に違いないが、個人的には、彼の妹である。非公式には、おりおり、兄顔もする宗盛だった。
「それは、勝つ日までと、知れきっておりましょう。おたgふぁい、その日までは、どんな艱苦かんく
にも耐えねばならぬ。── まして、みかどのおん母たるあなたは、つねに自若じじゃく
として、お座船の内に、つよみをお示しあらねば困る。それはすぐ、士気にかかわりますからの」
たしなめたが、女院の袖が、涙をつつむのを見て、急にあわて顔になり、
「いやなに、女性にょしょう
のおん身、つい、おん嘆きに滅入めい
るのも、さらさら、御無理ではおざらぬ。まして、今日のような不意の戦に追われてはの・・・・。おう、なお今宵も、軍議をひかえておる。くれぐれ、御自身を、おいとしみあれよ。みかどに次いでは、国母の君こそ、大事なおからだ・・・・」
宗盛は、すぐ、簾前れんぜん
を退さ がった。
そして、舷ふなべり
へ立ち出ると、神器を安置してある賢所かしこどころ
の辺から、広い船上をずっと見渡して、
「ここには、大理だいり
どの (平大納言時忠) が、陪乗ばいじょう
申し上げて、神器と玉体の御守護に当っておるはずなのに、大理どのは、どうされたかの、昼から、どこにも、顔を見せぬが」
あたりの人影にたずねた。
侍従少将有盛、平内左衛門へいないさえもん家長いえなが
など、ひざまずいて、居流れていたが、たれも答えようとはしない。何か、それについては、言いにくそうな気振りがあった。 |