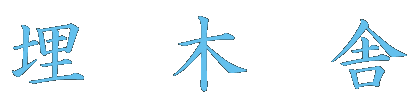すると、艫
に立っていた一群の武者のうちから、一人ずかずかと、それへ来て、
「お答え仕りまする」
と、宗盛の前に、ひざを折り屈かが
めた。
「そちは、たれか」
「能登どのの手に従う者、津つ
ノ判官ほうがん 盛澄もりずみ
にござりまする」
「盛澄か、答えとは、なんぞ」
「おたずねの大理卿だいりきょう
時忠ときただ どのには、仔細しさい
あって、他の一船に、御移乗をねがい、代って、それがしが、お座船の守りについておりまする」
「はてのう?・・・・。それや、たれのさしずで」
「能登どののおさしずによりまする」
「さては、けさ、屋島を離れるさい、能登守と大理どのとが、何か、口争くちいさか
いいたしたとか、聞いていたが、そのことからの、もつれでもあるのか」
「仔細は何も存じませぬが、ただ能登どのの仰せ付けのまま、大理どの御父子を、他の船に移し、かく申す盛澄が、神器ならびに玉体を、かたく御警固申し上げておりますので」
「それは分かったが・・・・はて、それだけでは、解げ
せぬことだの。何か、理わけ を聞いておらぬのか」
「もし、内大臣おおい
どのが、お見えあって、御不審のおたずねがあったら、仔細は、御評議の席にて、能登より直々じきじき
に申し上ぐるであろうと、かように、仰せられておりました」
「そうか、能登守には、そう申していたか。さらば、余儀ないわけがあったのであろう。盛澄、また有盛や家長らも」
「はっ」
「大理どのがおらぬとは、いささか心がかり。御守護の任、なおさら重い。抜かるまいぞ」
言い残して、宗盛は、待っていた小舟へ移った。
そして、自身の旗艦へ、帰ってみると、すでに軍議の座が開かれていた。能登守のとのかみ
教経のりつね を始め、小松中将資盛、左馬頭行盛、丹後侍従忠房、越中えっちゅう
盛嗣もりつぐ 、上総かずさの
忠光ただみつ 、悪七兵衛景清、源大夫李貞すえさだ
── などの公卿たちや、侍さむらい
大将の面々から、経盛、門脇かどわき
どの (教盛) などの長老まで、およそもれない顔が、船上せましとばかり詰めあっていた。
が、ただ一人、見えない顔がある。
平大納言時忠だった。
それと、時忠の子息、讃岐中将時実など、一連いちれん
の時忠派とも見られる人びとだけが、この夜、ここには欠けていた。 |