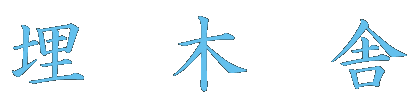遠見
の兵が、五剣山から急を告げて来たそれよりも少し前である。義経は、もう楯たて
の仮寝から目ざめてい、
「起きよかし人びと、身じまいすまば、早々に、義経の床几しょうぎ
まで寄り合い給え」
と、あたりの帷幕いばく
へ、みずから布令ふれ ていた。
附近の木蔭などに、ごろごろ眠っていた郎党たちはいうまでもない。幕とばり
の内に、前後不覚の態てい だった諸将も、義経自身の声に驚き。
「すわ、何事」
とみな跳ね起きた。そして、彼の将座を繞めぐ
り、主なる顔はたちまちそろった。
「・・・・?」
田代たしろの
冠者かじゃ 、畠山重忠、後藤兵衛、熊谷直実、伊勢三郎などの面々である。みな言い合わせたように、義経の後ろに控えていた一人の男を、いぶかしげに見まもりあった。
それは、桜間さくらま
ノ介すけ 能遠よしとお
だったが、たれもまだ彼をその者とは知ってはいない。
桜間ノ介も、うつ向きがちであった。敵人の中に一人置かれて、いかにも肩身が狭そうな姿に見える。
それを救いってやるかのように、。義経は、
「これは、阿波民部の弟、平家第一のもののふ、桜間ノ介能遠よしとお
ぞ」
と、一同へ告げて、
「今日、二月二月二十一日より、桜間ノ介こそは、深き思慮のあった、この義経に心を協あわ
せ、源氏の内に、身をいくことになったるなれ。申さば、おのおのとも一つ幕とばり
の戦友とも にはほかならじ。以後、隔てなく交まじ
われよ」
と、言った。
あえて、平家の降人こうじん
とは言わず、対等の者を引き合わせるような辞ことば
だった。
「・・・・・・」
後ろの桜間ノ介は、とたんに、ぼろぼろと落涙した。あわてて肱でその顔をかくした。
人びとは、かえって不審を深めたが、義経の言外の意味も、桜間ノ介の涙も、その後ではすぐ理解された容子ようす
である。むしろ粛しゅく とした気が漂った。
義経はここで、昨夜の出来事を、手短に、一同へ話した。
いや、それだけではない。
桜間ノ介から、そのさい義経が聞きとった重大な敵の機密も、ここへ集まった幕僚ばくりょう
だけには、打ち明けたのだった。
それが、どんな内容の機密かは、もう、言うまでもないかも知れない。
── 平家が待ちに待っている援軍の大将、田口左衛門教能のりよし
は、阿波民部重能しげよし の嫡子である。
言いかえれば、桜間ノ介
は、教能のりよし の叔父なのだ。
その教能のりよし
が、途中、屋島の変を聞き、部下三千余騎を引っさげて、急ぎに急いでいたのは当然なことだし、まだその消息を、叔父の彼が、知悉ちしつ
していたのも当然である。
が、桜間ノ介 から聞くまで、義経は、まったく、その方面の重大さに気づいていなかった。
彼らしからぬこと ── とも言えよう。しかし、一昨日、昨日、つい夕べの真夜半まよなか
までも、後ろへ一顧いっこ する暇もあったろうか。
襲よ
せては退き、退いては襲せて来る前面の敵、能登守教経のかけ引きだけにも、終日戦い疲れて、やっと半夜の憩いこ
いを、この岡おか に迎えたばかりと言っていい。
それなのに。
なお、三千余騎の新手が、海上の平家を援けるため、ここへ急いでいる
── と聞いては、義経が、慄然りつぜん
としたのも無理はない。
今さら、退くも残念。
玉砕か。
それも、おろかに思われた。
── 夕べ彼は、ひとまず、桜間ノ介の身を、弁慶にあずけてから、
「さても大難。この死地を、いかにすべき?」 を必死に案じて、身は横たえても、一睡もせずにいたのである。 |