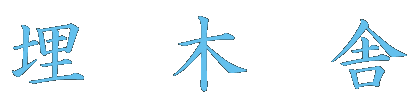その日、二十一日の未
ノ刻こく 前
(午後二時) には、もう雨龍うりゅう
ノ岡おか へ、
“──
談合、相あい 調ととの
うて候う”
という吉報を持った一騎が早くも帰って来た。
いかに義経が、ほっとしたかは、いうまでもない。どう誇張しても、そのおりの彼のよろこびを言い現すには足りない。
しかし、およそおなじぐらいな早さで、そのことは、平家の耳にも伝わっていた。
田口勢の多くの者のうちには、解軍とともに、ばらばらではあったが、小舟や馬などで、
「たとえ、修羅しゅら
の鬼ともなれ、この期ご に、御一門の人びとと離れられようか」
と、志度へ駈けつけて来た面々も、決して少なくはなかったのである。
宗盛以下、平家の人びとは、泣く泣く訴えて来たそれらの者の口から、
「田口殿は、源氏に降り、総勢は、群を解いて、ちりぢりになり申した」
と聞いて、これまた、どんなに愕然がくぜん
たる失望の底につき落とされたことだろうか。
そのうえにも、なお、平家方には、悪いことが重なって聞こえて来た。
田辺湛増たなべのたんぞう
の水軍やら、渡辺わたなべ ノ津つ
にあった源氏の水軍が、義経の先駆よりはるか遅れていたが、ようやく、軸艫じくろ
をそろえて、それらの船影も、北方の海上から、徐々に、近づいて来つつあるという島々からの諜報ちょうほう
だった。
「さても・・・・無念だが」
教経は、すぐ陸くが
の軍勢に、引き揚げを命じ、
「ここにいては、こんどこそ、海の上とて安全ではない。このうえは長門へ降くだ
って、権中納言 (知盛) どのの手勢と一つになろう」
その夕べ、三百余艘、帆影をそろえて、讃岐さぬき
の海を後に出て行った。
海うな
づらも空も夕焼けに燃えていた。
虹色にじいろ
の屋島の影を振り向いて、能登守教経は、船やぐらの上に、ただ一人、泣き笑いとも自嘲じちょう
ともつかない嘯うそぶ きをもらしていた。
「おもしろい、おもしろいほど、事ごとに食い違ってくる。不運とは、こうしたものか。どこまで、人と運が、もつれあうか、もてあそばれて行くものか、あまんじて不運と闘ってみるのも愉たの
しくないことはない。どうせ落ち目の運命ならば、この落日らくじつ
のように、荘厳そうごん でありたいものだ。せめて平家の末路は荘厳に
──」 |