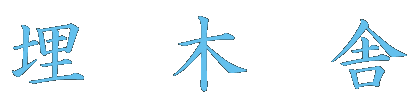その夕べ、義経は、八栗半島の一峰
へ登っていた。暮るるも忘れて、立ちつくしていた。
彼の面おもて
ににも赤かった残照ざんしょう
はいつか薄らぎ、遠くに見えていた平家の船群も、落日の中へ溶け込んでしまったように、やがて水平線の西へ没し去っていた。
── 戦いくさ
は休や んだ。
平家はことごとく西へ落ちてゆき、あとの屋島や牟礼むれ
の浜には、落寞らくばく としたものだけが残った。血なまぐさい二日間の狂乱から醒さ
めて、元の自然に返った磯のしぶきや峰風の声には、そこらで果てた幾多の魂魄こんぱく
が、行くところもなく、なお、さまよっているかのように思われる。
「殿、殿・・・・」
果てしない義経の佇たたず
みに、郎党たちが、口々に、うながした。
「雨龍うりゅう
にあるお味方も、お案じ申しておりましょうず」
「みな、殿のお姿を待ちぬいておるやと思われまする。── 眼にも御覧ぜられしとおり、ついに平家は見得も捨てて落ち行きました。敵の三百余艘、はや一隻だに見えませぬ。いざ、御帰陣あって、一同とともに、吉例の勝鬨かちどき
を」
「・・・・・げにも」
義経は、われに返って、
「今宵はもう、敵の一兵も、この地にはいないわけだったな」
すぐ、歩き出したが、その影は、なぜか淋しそうであった。
弁慶、忠信、有盛などの郎党は、さっきから義経の胸のうちを、彼らは彼らなりに、こう忖度そんたく
していた。
おそらく、義経の心では 「もし、ここに何十艘かの船だにあらば、一門平家はおろか、みかどのお座船も神器も、みすみす、見遁みのが
すことではないのに」 と、いと口惜しく思って、敵の行方をあのように見送っていたものにちがいあるまい ── と。
が、義経の眸め
は、そんな妄執もうしゅう を追っていたのではない。
“
── われ勝てり ” と思ったとたんに、彼は、たまらない淋しさに襲われたのであった。
宇治川や一ノ谷では、こんな矛盾は、覚えもしなかった。
しかも、屋島攻めは、その時以上な困難が予想され、捨て身の戦法に出たのである。
──
生きている今が、勝ったことが、不思議でならないほどなのだ。従って、勝利の快感もそれに比例していいはずなのに、彼の胸は、少しも凱歌がいか
をたぎらせて来ない。
── 自分でも怪しまれるほどそれは意外な実感だった。
なぜか。なぜ、嬉しくないのか。
ひそかに、自分へ問いながら、彼は、黙々と、もう薄暗い山路をふもとへ向かっていた。
総じて、こんどの一戦は、いわゆる奇捷きしょう
というもので、源氏が強かったのではない。
余りにも平家に策がなさすぎていたのだと思う。いかに多くの兵船を持ち、弓箭きゅうせん
は並べ立てても、平家勢は、ほんとの意味の軍隊といえるほどな軍ではない。
義経は、平家というものの実体が、この屋島へ来て初めてよくわかった気がした。
上には、幼いみかどとおん国母こくぼ
を擁し、あまたな女房やら無用な老人だの女童めわらべ
までを連れているのだ。それは幾十という大きな家庭の延長であり、家庭の寄せ集めといってもとい。
一ノ谷の合戦では、武者と武者との直面だけで、そうしたいじらしい者たちが、楯の蔭にいることは眼に見なかった。けれどこの屋島では、まざまざと、義経もそれを目撃した。
「畢竟ひっきょう
、平家人へいけびと は、半公卿はんくげ
ともいうべきか。そんな長袖の人びとや、女おんな
わらべの群を討ったりとて、なんの誉れ。・・・・わけて建礼門院を始めとして、幾十の母と子も、あわれ、あの船影のうちにいたろうに」
亡ほろ
びる者への憐愍れんびん というものか。
ともすれば彼は、その余りな、あわれさにとらわれ、勝者の誇りも、よろこびまでも、暗くされてしまうのだった。 |