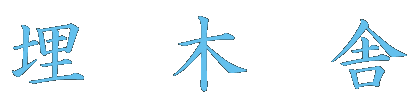言うまでもなく、鎌倉武門は、徐々に、武家中心の新幕府を形作りつつある鉄の組織だった。
義経の地位も、その組織からいえば、単なる組織の一員にすぎない。
けれど、彼の本質は、到底、組織の子ではなかった。ややもすれば、その性情は、紊
すつもりもなく、組織を紊すものとなりやすい。
たとえば。
今度の屋島作戦なども、すべて、彼一個の独断と勇気のもとになされ、梶原景時かじわらのかげとき
という軍艦の存在など、まったく、無視し去っていた。
若さにまかせ、ただ自分一個の功名を急ぐのであろうか。いや、そんな彼ではないことは、彼を知る者ならみな知っている。
彼はただ
「平家を討つのは、わが天命ぞ」 という信念に他ならない。
平家は、不倶ふぐ
戴天たいてん のかたきと、少年の日から思い込んでいた。それが彼の脊柱せきちゅう
になっていた。
兄頼朝の旗挙げに馳は
せつけたのも、一ノ谷の合戦から、屋島攻めにいたるまで、つねに先陣を斬って来た一途いちず
な姿も、すべてこれ “仇あだ
なる平家” 目がけてであった。
しかし、ふと今。
彼が淋しさにくるまれたのは、少年の日から抱いて来たその一念が、今日の如く遂げられてみると、かえって逆に、敵の弱さや、その悲運な集団に、人間的な思いを寄せずにいられなくなったからであった。
──
ことに、自分の母の常盤ときわ
を胸にうかべると。
この夕べ、屋島をあとに落ちて行った平家の内にも、幾多、常盤にひとしい悲運な母ができているにちがいない。また、自分の身の上と似たような薄命の子が、平家からも、行く末、たくさんちまたに投げ出されることであろう、と思う。
義経は、つい、そんな情にもとらわれた。
それは、彼があくまで私情の子であって、鎌倉どのの組織と目標を代行する大将でなかった証拠でもあった。
「これ以上にも、あの弱き者たちを、敵と呼び、仇と憎んで、どこまでこの弓矢にて、追いつめ、追い亡ぼさねばならぬのか」
と、今ではその遂行が辛つら
くなっていたのである。
もっと深くその心に立ち入れば、これ以上な追撃には、自信をなくしていたほどかも知れなかった。
しかし。── その宵の雨龍うりゅう
ノ岡おか は、まるで歓呼の坩堝るつぼ
だった。
勝者の快に、踊り狂い、たれ一人、義経の心事を知った者はいない。
死を賭か
けた武者にすれば、それは当然、狂喜に値する勝利の夜だった。義経のひそかな淋しみなどは、およそ武人には通用しない彼のみの感傷といえよう。── 義経もそれを知らないわけではない。
で、彼も岡の陣門へ入ると、つねの如き態度に返っていた。そして、自身の幕舎とばり
の前に立つと、
「三郎、奉行を」
と、さっそく、勝鬨かちどき
の式を、伊勢三郎に命じた。 |